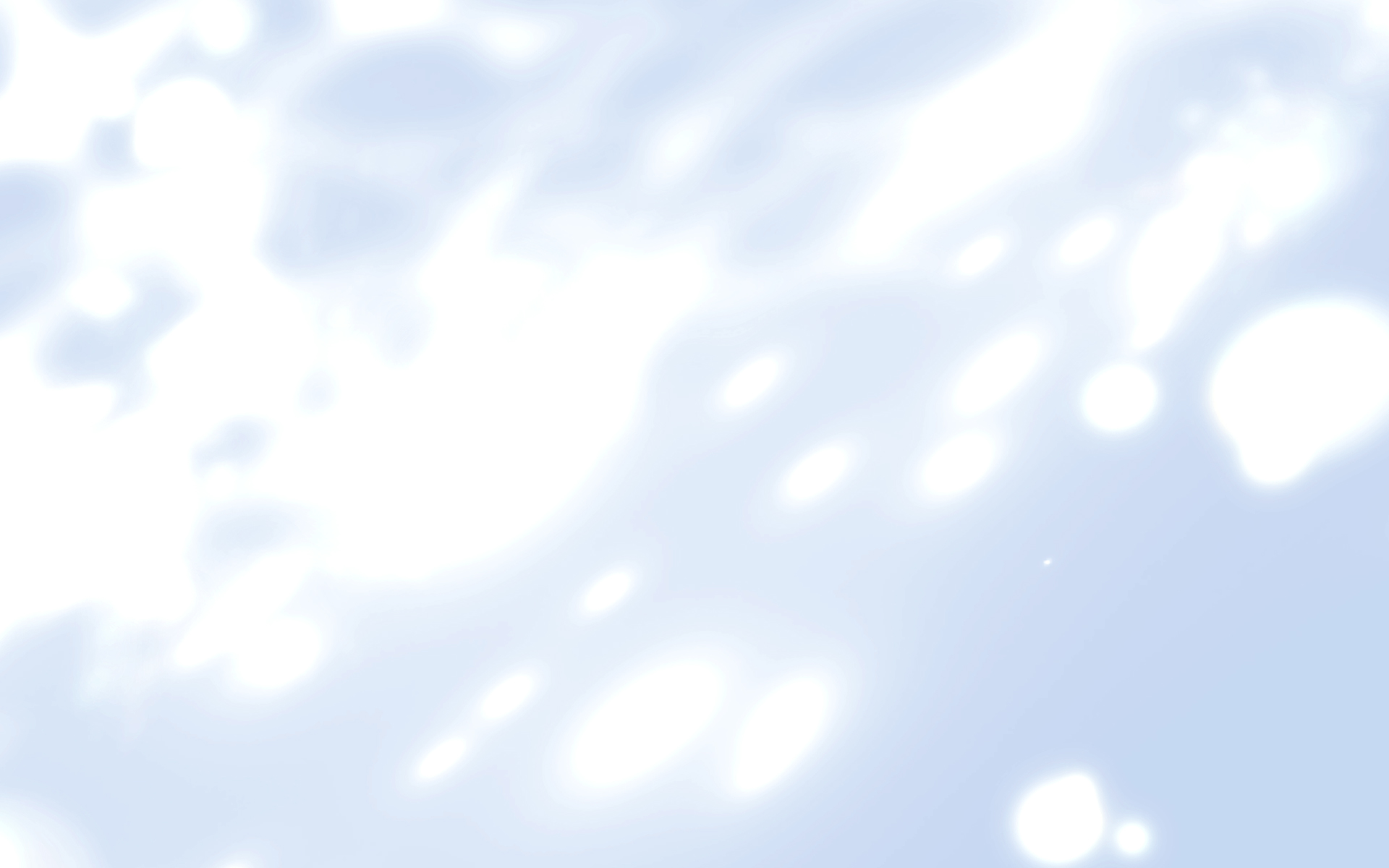
症状から探す
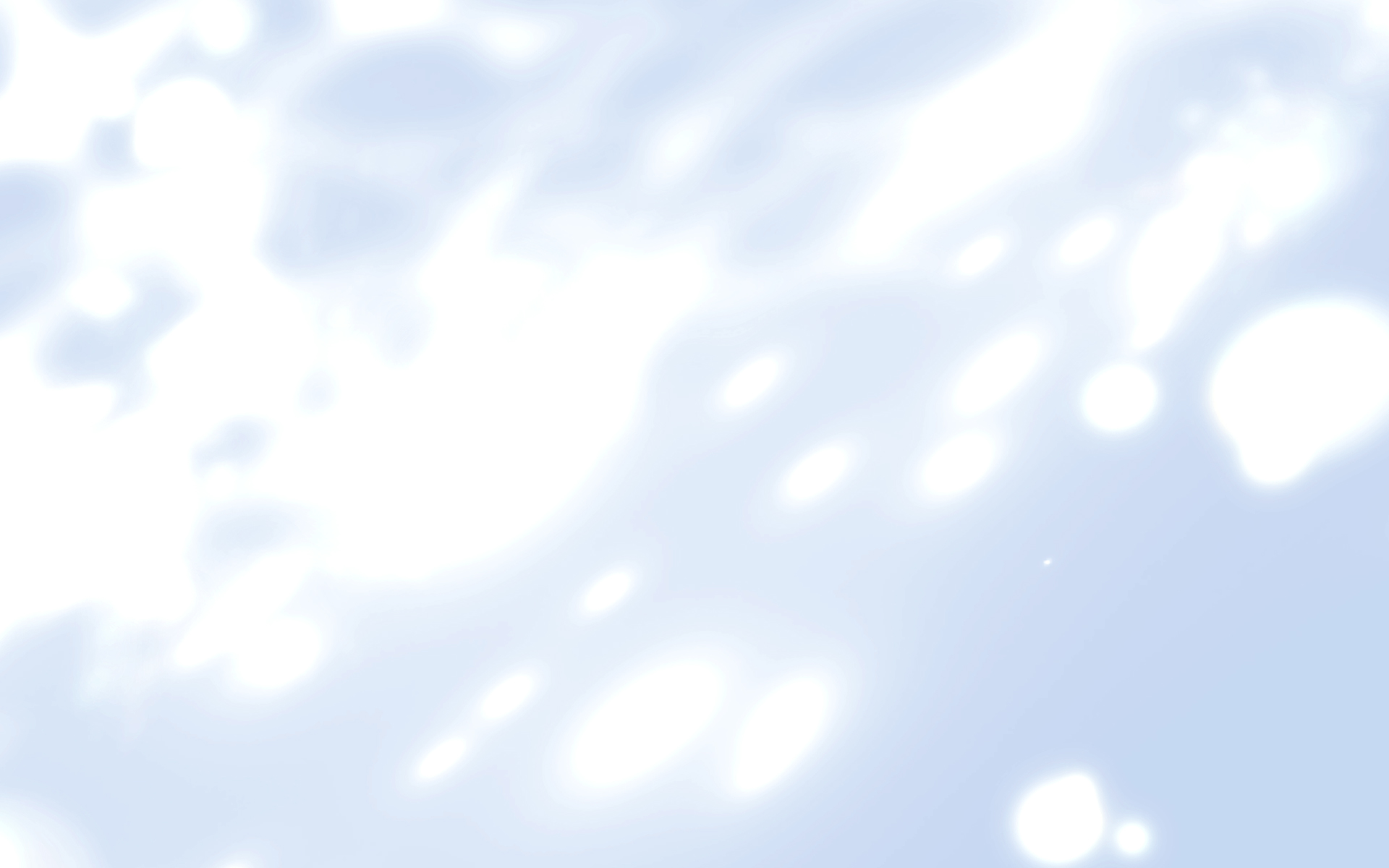
症状から探す
胸の痛みや圧迫感、絞扼感(締めつけられる感覚)は、心臓や血管に関連する疾患のサインかもしれません。朝の通勤途中で階段や坂道を上る時やストレスを感じた時、夜間や早朝に胸が締めつけられ冷汗を伴う痛みが現れるような場合、狭心症や心筋梗塞などの重篤な疾患の可能性があります。放置すると重症化し命に危険を及ぼす恐れがあるため、早めの受診が大切です。血液検査、胸部レントゲン、心電図、心エコーなどの検査で迅速に評価を行い、必要に応じて連携医療機関に紹介いたします。一方で、チクチクする痛みや狭い範囲に限局する痛みは重篤な疾患ではない可能性が高いです。症状のある方はお気軽にご相談ください。
階段や坂道で息切れがしたり、夜横になって寝ると息苦しくなるような場合は、心不全の可能性があります。心不全は心臓が全身に十分な血液を送り出せなくなる状態で、高血圧や心筋梗塞、弁膜症、不整脈が原因となることが多いです。その他にも肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、肺炎など呼吸器疾患の可能性もあります。当院では血液検査(BNP)、心電図、胸部レントゲン、心エコー検査のほか、スパイロメータで肺機能を調べることで息切れの原因の診断が可能です。早期診断と治療が重要なため、日常生活に支障が出る前に早めに循環器内科を受診しましょう。
手や足のむくみ(浮腫)は、様々な理由で血液やリンパ液の流れが滞っているサインです。特に両足が慢性的にむくむ場合、心不全や深部静脈血栓症などの心臓や血管の病気の可能性があります。他にネフローゼ症候群、腎不全、肝硬変、内分泌疾患(甲状腺機能低下症)、脚気など心臓以外にもさまざまな要因が挙げられます。一時的なむくみだと放置しがちですが長引く場合は注意が必要です。当院では血液検査や胸部レントゲン、心エコー、下肢静脈エコーなど、むくみの診断に必要な検査に随時対応いたします。悩まずにお気軽にご相談ください。
疲れやすい、手足が冷たい、だるい、易疲労感などの症状は、心臓から十分な血液が全身に送れていないこと(低心拍出量状態)が原因かもしれません。心不全、弁膜症(大動脈弁狭窄症、僧帽弁逆流症、三尖弁逆流症など)、虚血性心疾患、心筋炎、心筋症などの心臓病が原因の可能性があります。その他、甲状腺機能低下症、貧血、肺疾患、糖尿病、自律神経失調症、睡眠時無呼吸症候群などが原因となります。疲れやすい、だるいと感じる場合は、「年のせい、気のせいだろう」などと自己判断せず、お早めに循環器内科にご相談ください。
自分の心臓の鼓動を意識することや不快に感じることを動悸といいます。突然の激しい動悸や脈の乱れは、不整脈の可能性があります。心房細動という不整脈は心臓内に血栓ができやすく、脳梗塞のリスクが高まるほか、頻脈が続くと心不全を発症します。動悸が短時間で治まっても、「一時的だから大丈夫」と自己判断せず、早めに専門医の診断を受けましょう。当院では心電図を長めに記録し、不整脈に関連する所見がないかしっかり確認し、小型軽量の24時間ホルター心電図で詳細に評価します。さらに不整脈を起こす心臓病が隠されていないか、血液検査や胸部レントゲン、心エコー検査を行い診断します。健診で心電図異常を指摘された方もお気軽にご相談ください。
失神とは「突然発症し、数秒間から数分後に自然に回復する、体勢の保持が不可能な意識消失発作」と定義されます。脈が遅い場合や、めまい、立ちくらみ、意識が遠のく、失神する場合は、洞不全症候群や房室ブロックなど徐脈性不整脈の可能性が高いです。その他、心房細動や心室頻拍など頻脈性不整脈の可能性もあります。失神は致命率も高く正確な診断が必要です。神経反射を介した失神(血管迷走神経反射、排尿失神、Valsalva手技)、一過性脳虚血発作、低血糖、薬剤性、うつ病などの精神疾患が要因となる場合もあります。専門医の診察とエコーやホルター心電図などの検査を受けていただき、心疾患がないか調べることが重要です。ヘッドアップチルト試験や植込み型心臓モニタ(ICM)などの高度な検査が必要となる場合は連携医療機関に速やかに紹介いたします。
背中や腰の痛みは心臓や血管とは関係ないと思われがちですが、大動脈解離や大動脈瘤、狭心症、腎梗塞などの可能性があります。突然の激しい痛みや、痛みが長時間続く場合は要注意です。大動脈解離では、背中や胸部の引き裂かれる痛みに続いて、足の痛みが出たり動かしにくくなることがあります。大動脈の末梢まで血管の裂け目が広がり、血流が低下することが原因です。対処が遅れると命に関わることがあるため、症状でお困りの方は循環器内科にご相談ください。整形外科・泌尿器疾患などの可能性もありますが内科から信頼できる医療機関に橋渡しをいたしますのでお気軽にご相談ください。
歩行時に、下肢の特にふくらはぎの部分に痛みや不快感が出て、休むと良くなる症状は間欠性跛行(はこう)と呼ばれ、末梢動脈疾患の可能性が高いです。動脈硬化で手足の動脈が狭窄あるいは閉塞し、末梢側に酸素や栄養を十分に送り届けることができなくなった状態です。喫煙や高血圧、糖尿病、脂質異常症があるとリスクが高まります。この病気は徐々に進行し、冷感、しびれ、安静時の痛み、潰瘍・壊死といった症状が現れてきます。血栓が形成されると急速に悪化するケースもあり迅速な対処が必要です。当院では下肢の色調や潰瘍の有無を確認し、触診やABI検査をもとに診断します。その他、神経根圧迫(下肢下方に広がる)、股関節炎(外側腰部、大腿部の痛み)、脊柱管狭窄症(両側臀部、下腿後面の痛み)などの整形外科疾患が原因と考えられる場合には連携医療機関にご紹介いたします。
どの症状も、早期発見・早期治療が重要です。
少しでも気になる症状がある場合は、自己判断せずに循環器内科を受診してください。
TOP