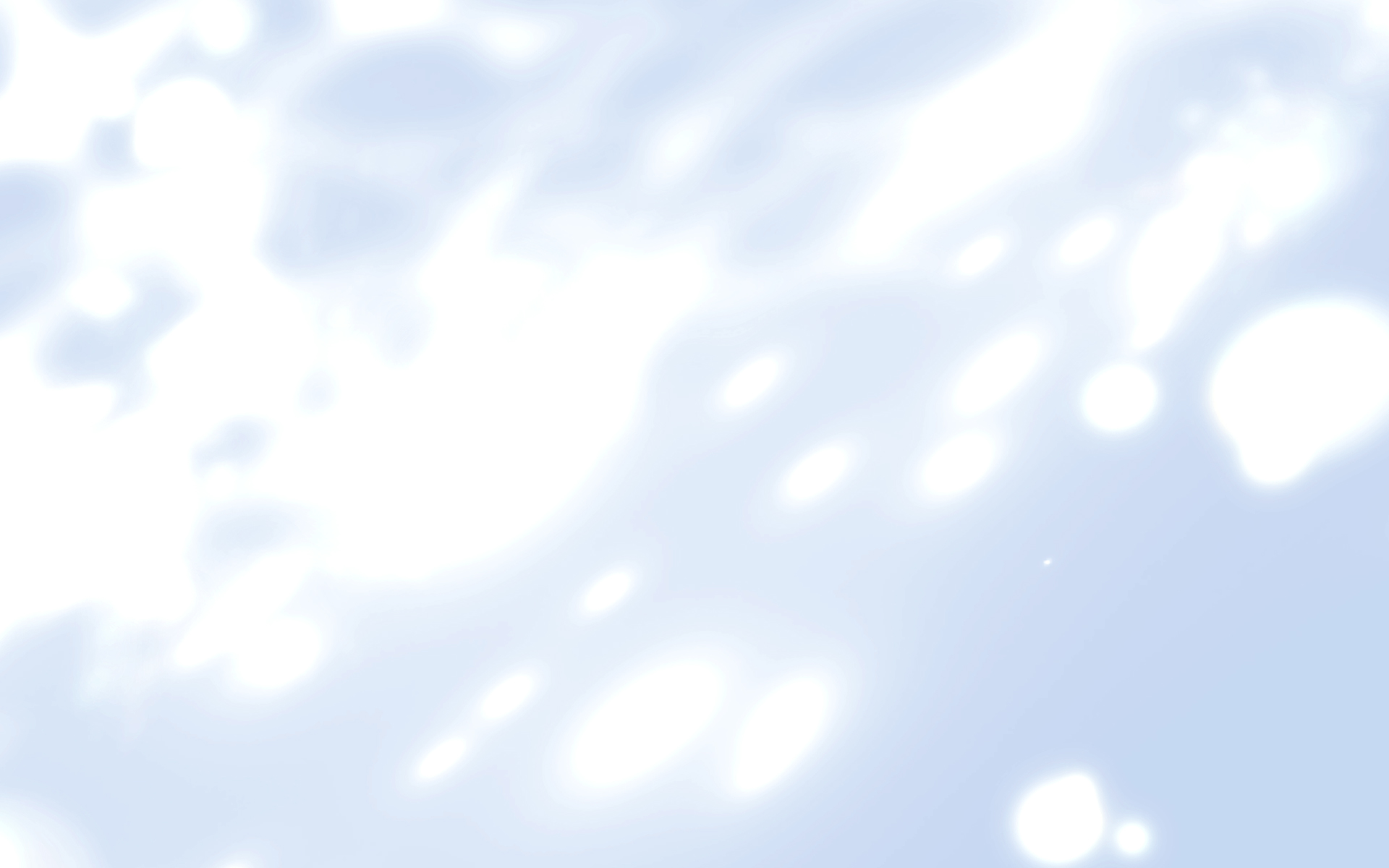
循環器内科
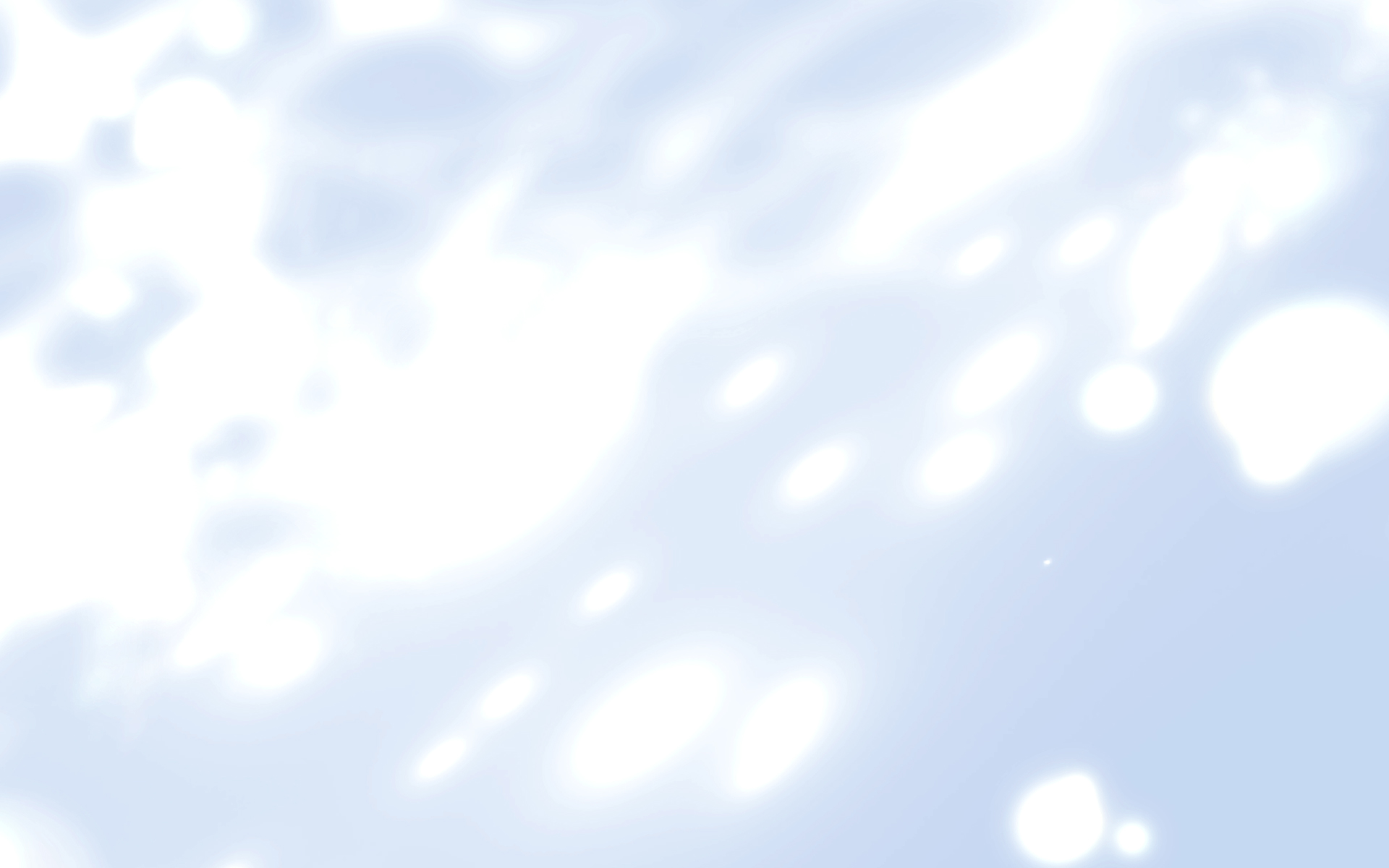
循環器内科

循環器内科では、全身に血液をめぐらせる心臓や血管の病気を専門的に診療します。狭心症・心筋梗塞、心臓弁膜症、心不全、不整脈などの心臓の病気や、動脈硬化症、動脈瘤などの血管の病気に幅広く対応しています。循環器病の主な原因である高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、肥満などの生活習慣病を適切に管理しながら治療することが重要です。当院では、日本循環器学会などのガイドライン指針に従い、他の連携医療機関と協力しながら、皆様の循環器病の予防と早期発見、正しい診断と治療、慢性期における再発防止のためにスタッフ一同全力を尽くします。
気軽に相談できる“心臓と血管のかかりつけ医”としてお役に立てましたら幸いです。
人口の高齢化に伴って、弁膜症を有する患者さんは増加しています。弁膜症の患者さんにとって最も重要なことは、ガイドラインを遵守した心エコー検査による正確な重症度診断を受けていただくことと、適切な治療法を知っていただくことです。当院では弁膜症診療に長年携わってきた院長の経験と専門的な知識をもとに、高精度の心エコー検査を活用した弁膜症外来を実施しております。患者さんにはより良い治療法やフォローアップについて丁寧にご説明し、手術をお勧めする場合には、成績の良い病院や信頼のおける心臓血管外科医に直接ご紹介いたします。まだ手術適応ではない患者さんや、手術後の患者さんも数多く診療しており、定期的なエコーフォローアップや術後管理も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。当院では院内迅速検体検査、心電図、胸部X線、心臓・血管エコー、運動負荷心エコー、ホルター心電図、呼吸機能、睡眠時無呼吸検査などの各種検査機器を取りそろえており、いつでも検査が可能です。気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。
弁膜症のフォローや心臓病の治療後の定期的なエコーを受けないまま気づくと何年も経ってしまった方、予約を取りそびれてそのままになってしまった方も日常臨床ではよくお見かけします。当院ではそのような方々の検査にも随時対応いたします。お気軽にご相談ください。
狭心症は心臓に血液を送り、酸素と栄養を供給する冠動脈の血流が不足することによって、心筋が酸素不足となる病気です。主に動脈硬化で冠動脈が狭くなり、心臓への血流が一時的に滞るために発症します。労作性狭心症の多くは、「階段を上ったり、重いものを持ち上げたり、坂道を歩くと胸が締めつけられたり苦しくなる、安静にすると楽になる」といった症状がみられます。前胸部以外にも、腕、肩、頸、みぞおちなどの痛み(放散痛)が出る場合があります。歯やのどが痛むケースもあります。狭心症を放置していると冠動脈が閉塞して心筋梗塞となり、生命に関わる危険な状態になる場合がありますので、症状のある方は早急に循環器内科を受診ください。
冠攣縮性狭心症は、夜、就眠中、明け方などに胸が苦しく押さえつけられるような発作が起こる病気です。冠動脈が一過性に痙攣(けいれん)を起こして収縮し、血流が一時的に途絶えるために生じると考えられています。日中に発作が起こることもあり、痛みの性質や部位は労作性狭心症と同様です。冠動脈の攣縮(けいれん性の収縮)も、動脈硬化の進行過程でみられる現象と考えられています。このような症状がある場合も早急に循環器内科での検査・診断を受け、治療を開始することが重要です。正確な診断のために数日間のカテーテル検査入院が必要となる場合があります。
心筋梗塞とは冠動脈が突然詰まって血流が途絶えてしまい、心筋に酸素と栄養が供給されなくなり、その領域の心筋が壊死してしまう病気です。胸が焼けるように激しく痛み、締めつけられる症状が現れ、多くは冷や汗や嘔吐を伴います。この発作は長く続き、数時間から翌日に及ぶ場合もあります。このような場合は至急、救急車を呼んでください。高齢者や糖尿病患者では感覚が鈍く、胸痛を自覚しないこともあり、食欲低下や元気が無いといった症状であったりすることから見落とされるケースも少なくないので注意が必要です。心筋梗塞を放置すると、心不全や危険な不整脈が出て生命に関わる危険な状態になるため、胸痛を感じた方は早めに循環器内科を受診ください。
心臓弁膜症とは心臓の弁に障害が起き、本来の機能を果たせなくなった状態を指します。心臓内部には大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁があり、いずれの弁にも弁膜症が生じ得ます。大きく分けて、弁の開きが悪くなり血液の流れが妨げられる「狭窄」と、弁の閉じ方が不完全になり血流が逆流してしまう「逆流(あるいは閉鎖不全)」があります。先天的な形態異常の場合や、加齢による変化、リウマチ熱後遺症、心筋梗塞などに伴って生じる場合があります。弁膜症が進行して弁の機能が悪化すると、次第に心臓の負担が増え、心不全症状が現れてきます。典型的な症状として、息切れ、胸の痛みや違和感、めまい、意識を失う、疲れやすいなどがありますが、弁膜症に特有の症状はありません。ご本人に症状があっても加齢によるものと考えてしまったり、周囲の人からも見逃されがちです。「健診で心雑音を指摘された」、「心エコー図検査で弁の異常を指摘された」という場合は、心エコー診断経験の豊富な循環器専門医を受診ください。
心不全とは、心筋梗塞や弁膜症、心筋症などの疾患によって心臓のポンプ機能が低下し、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなることで、息切れ、倦怠感、むくみなどの症状が起こってしまう病気の総称です。日本の心疾患・脳血管疾患を合わせた循環器病の死亡率は、がんに次いで第2位となっており、進行した心不全(ステージCおよびD)の予後は不良です。そのため、軽症(ステージAおよびB)のうちから心不全の発症予防と治療を重点的に行うことが重要と考えられています。平地では何ともなくても、階段を上ったり、重いものを持って息切れが出る場合は、心不全症状の可能性があるため、早めに循環器内科を受診ください。
不整脈とは、心臓の電気的興奮のリズムが異常になった状態の総称です。大きく分けて脈がとぶように感じる期外収縮、脈が速くなる頻脈、脈が遅くなる徐脈の3つがあります。心臓は1日に約10万回も拍動していますが、時に規則正しくない電気信号によって不規則な動きをしてしまうことがあり、不整脈は誰にでも起こり得ます。不整脈の原因の多くは心臓の病気ですが、甲状腺疾患、肺疾患、老化、体質、ストレス、睡眠不足、過労などによっても不整脈は起こりやすくなります。ご自身で気付かず、健診ではじめて不整脈を指摘される方もいます。不整脈によっては心不全や失神発作、脳梗塞を起こす危険なものもあります。不整脈を指摘されたとき、脈の不整や動悸を感じたときは循環器内科を受診しましょう。放置しておいてもよい不整脈なのか、危険な不整脈に発展するものかなど、よく説明を聞いて適切な指導を受けることが大切です。
末梢動脈疾患とは、冠動脈以外の末梢動脈に病変が起こる疾患の総称です。主に足の血管が動脈硬化によって詰まってしまう病気を、従来から下肢閉塞性動脈硬化症と呼びます。足に冷感やしびれ、歩行中の痛みを感じ、休むと症状が消失する間欠性跛行という症状にはじまり、重症化すると手足に潰瘍ができ壊死することもあります。50歳以上の男性に多い傾向があり、糖尿病・高血圧・肥満・喫煙などが原因と考えられています。末梢動脈疾患を発症した場合には、下肢だけでなく全身の血管も動脈硬化が進んでいる可能性が高いのでご相談ください。
日本高血圧学会では診察室血圧で140/90mmHg以上、家庭血圧で135/85mmHg以上を高血圧と定めています。最近では血圧の正確な評価のために家庭血圧が重視されています。高血圧を放置すると血管が動脈硬化を起こし、脳卒中や心臓病、腎臓病などの病気を発症する危険性が高まります。減塩食、運動、減量を中心とした生活習慣の改善が治療の基本ですが、より確実に血圧を下げるためには降圧薬の内服が必要となる場合が多いです。血圧を適切なレベルに下げることで重大な脳心血管病のリスクを減らし、寿命を延ばすことが可能です。治療によっても血圧がなかなか下がらない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
脂質異常症(高脂血症)とは血液中の脂質が異常な値になる病気です。すなわち「悪玉」LDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド; TG)が増えたり、「善玉」HDLコレステロールが減った状態を指します。脂質異常症を放置すると、脂質が血管の内側に溜まって動脈硬化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞の発作を招くリスクが高まります。自覚症状がなく、健診で見つかった場合は生活習慣の是正とともに適切な薬物治療を考慮します。遺伝性の「家族性高コレステロール血症」では特に治療を強化する場合があります。
TOP