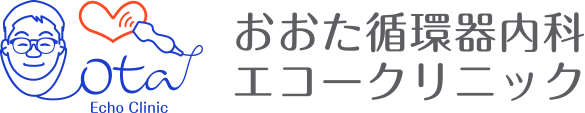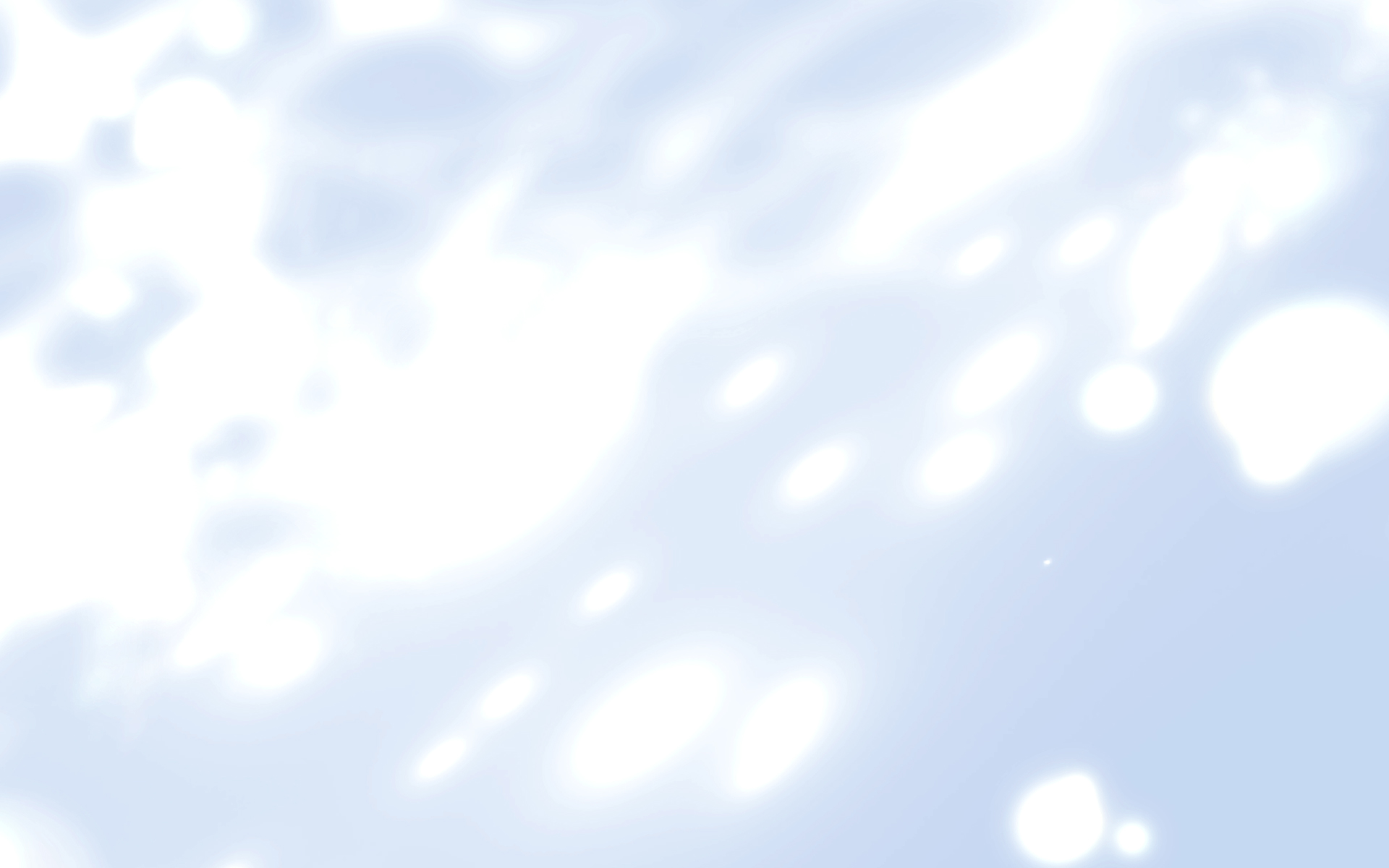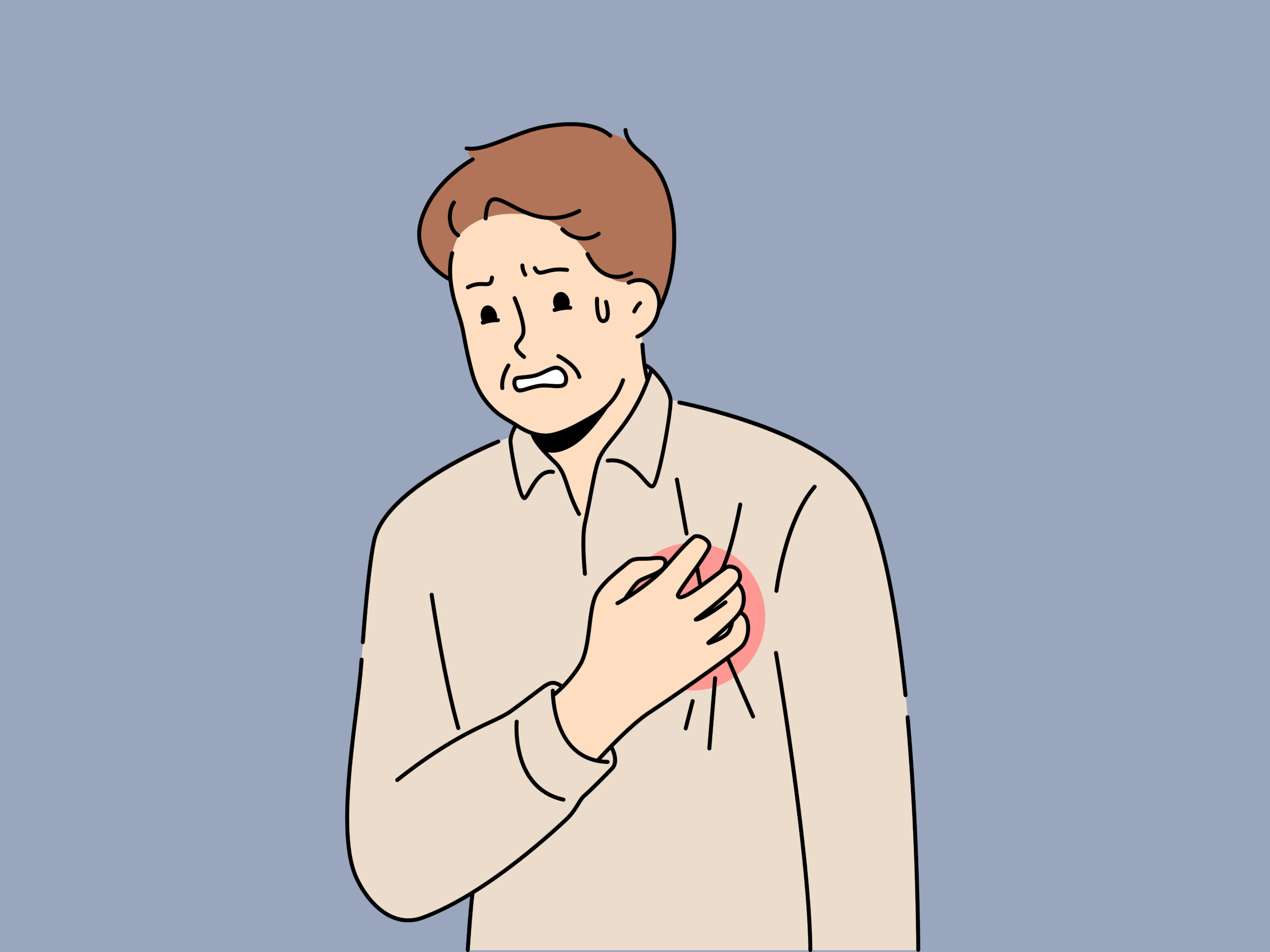2025年10月30日

みなさん、こんにちは。院長の太田光彦です。
すっかり寒くなってきましたね。日によっては朝晩の寒暖差が激しく、血圧が変動しやすい季節です。冬は心臓病のリスクが高まりますので、体調に不安がある方はかかりつけ医に相談をしましょう。
さて、前回、心臓弁膜症は65歳以上の約10人に1人が罹る病気というお話をしました。
しかし、過剰に心配する必要はありません。治療の選択肢が増え、体への負担を抑えながら治すことができます。
今回は具体的な治療法についてお話します。
本記事の概要
心臓弁膜症は、進行しても自覚症状が乏しいため、早期発見と適切な治療が大切です。本記事では、循環器専門医が保存的治療・弁形成術・弁置換術・カテーテル治療(TAVI)といった代表的な治療法をわかりやすく解説。手術のタイミングや人工弁の種類、治療後の生活の注意点まで幅広く紹介します。治療の選択肢を知ることで、患者様が安心して自分に合った方法を選べるようサポートします。
心臓弁膜症と診断されたら?症状の進行度で変わる治療の選択肢
心臓弁膜症は自然に治る病気ではないので、重症度に応じて治療方針を決めます。静かに進行していくため、適切なタイミングで外科的治療(手術)を受けることをすすめています。
この重症度を決定するために最も重要な検査が心エコー検査です。当院では弁膜症の重症度を正しく評価するために、精度の高い心エコー検査を丁寧に行い評価しています。
軽症〜中等症は、手術をしない「保存的治療」が中心
軽症・中等症の場合は、定期的に検査を行って経過観察をします。軽症であれば3~5年ごと、中等症なら1~2年ごとが目安です。
むくみや息切れ、胸痛など症状がある場合、薬で心臓への負担を減らします。これは対症療法なので、弁そのものを治すわけではありません。また、血圧が高い方には、食事や生活習慣の見直しにより血圧を下げるよう指導をしています。
重症の場合は手術が検討される
正常な働きをしなくなった弁は薬では治らないため、弁を修復する手術が必要となります。心臓弁膜症の重症度、症状、患者様の状態など総合的に判断をし、外科的治療を選択します。
心臓弁膜症の外科的治療法

近年、身体への負担が少ない手術方法が増え、治療の選択肢も広がりました。とはいえ、患者様の多くが65歳以上の高齢者なので、手術に対して消極的な方もいます。その場合は、手術を受けるメリットとリスクを説明し、不安をひとつひとつ解消しながら、納得できる治療法を一緒に見つけるようにしています。
弁を修復または取り替える「開胸手術」
胸を開き、一時的に人工心肺装置を用いて、心臓を切開して行う手術です。
患者様自身の弁を温存し、形を修復して弁の機能を回復させる「弁形成術」と、悪くなった弁を取り除き、生体弁もしくは機械弁に取り換える「弁置換術」があります。どちらの術式を選択するかは、術前の検査結果を元に患者さん最終的には医師が判断します。一人ひとり状態が異なりますので、手術時にどの箇所に問題があるのかを確認して、最終決定を行います。
手術後の生活を考慮して、一人ひとりに適した治療法を選択
弁置換術は、患者様自身の弁が修復のできないような場合に、人工の心臓弁に取り換える手術です。人工弁には「生体弁」、「機械弁」の2種類があります。
・生体弁:ウシやブタの生体組織を用いた人工弁。10~15年で劣化や石灰化が起こるため、再手術を行う可能性が高くなります。
・機械弁:チタンやカーボンなどの素材でできた人工弁。耐久性が高いものの血栓ができやすいため、血液をサラサラにする薬を生涯飲み続けなければなりません。
どちらが適しているかは、患者様の年齢、症状、生活スタイルによって異なります。
体への負担を抑えた新しい治療法「カテーテル治療(TAVIやTEER)」
開胸せずに、太もものつけ根や首の血管からカテーテル(医療用の細い管)を挿入し、大動脈弁まで生体弁を運ぶカテーテル治療(TAVI)もあります。日本では、2013年に保険適用になり、大動脈弁狭窄症の治療に用いられています。その他、僧帽弁閉鎖不全症に対する治療として経皮的僧帽弁接合不全修復術(TEER)も2018年から保険適用になっています。
高齢者や患者様の持病によっては開胸手術が困難な場合があるため、できるだけ身体に負担をかけないよう開発されました。今後は三尖弁閉鎖不全症に対するカテーテル治療も日本で保険適用となる見込みです。
適切な治療は「ハートチーム」で決める
手術は健康寿命を長くするために行う治療です。心臓弁膜症の場合、年齢や体力の問題から「手術はしなくても……」とお考えになる患者様もいらっしゃいます。手術をするリスクがないとはいえませんが、治療すると、症状が改善し、健やかに過ごせます。
私はたくさんの患者様と向き合い、説明を重ね理解をしていただけるよう努力してきました。医師が押し付けるのではなく、治療を受ける患者様自身が理解、納得することを大切にしています。そのためにも、循環器内科医一人が判断するのではなく、外科医、麻酔科医などさまざまな分野の専門家が連携する「ハートチーム」を組み、患者様にとって最適な治療法を選択しています。
手術後の生活で気をつけたいこと

開胸手術やカテーテル治療を受けた後は、普段通りの生活に戻ることができます。ただ、感染症には注意が必要です。血液中に細菌が侵入し、人工弁に付着すると感染性心内膜炎になるリスクもあります。特に歯科治療を受ける際には、心臓弁膜症術後であることを事前に歯科医へ申告し、抗菌薬を飲む必要があるかどうかを相談しましょう。
定期的な心エコー検査で心臓の状態をチェック
手術後も経過観察が必要です。新しい弁が正常に動いているか、心臓の機能がどうかを確認します。医師の指示に従い、指定された期間に心エコー検査を受けましょう。
体重や血圧を測り健康状態を確認
病院での検査だけでなく、患者様ご自身で体調の変化に気づけるよう体重、脈拍、血圧を測ることをおすすめしています。特に血圧の上昇は心臓への負担になりますので、決まった時間に測定し、異常がある場合はすぐに受診しましょう。
積極的に外出し、適度な運動を行って
体力が回復してきたら旅行やスポーツも楽しめます。適度な運動は、体力・健康維持に欠かせませんので、買い物や散歩など積極的に外に出ましょう。
ただし、いきむような動作は血圧が急激に上がってしまうので避けてください。このスポーツをしていいのか?と不安があるときは、医師に相談をするといいですね。
心臓弁膜症は、治療法が確立されている病気です。自覚症状が現れた時点では、重症というケースもありますが、進行スピードが速い病気でもありませんので、過剰に不安になることはありません。体に負担が少ない治療も公的保険が適用されます。
定期的に検査を行い、主治医と相談をしながらご自身が納得できる治療法を選択してください。
FAQ
Q1. 心臓弁膜症の治療はどのように決まりますか?
A. 症状の進行度や心臓の機能、患者様の体力や年齢を総合的に判断して治療方針を決定します。軽症では経過観察が中心ですが、重症の場合は外科的治療(手術)が検討されます。
Q2. 手術を受けるタイミングはいつが良いですか?
A. 重症化して心臓の機能が低下する前に行うのが理想です。症状や検査結果を見ながら、主治医と相談して適切な時期を見極めましょう。
Q3. 高齢でも手術を受けられますか?
A. はい。身体への負担を抑えるカテーテル治療(TAVIやTEER)など新しい選択肢が増えています。年齢だけで判断せず、医師やハートチームと相談して決めることが大切です。